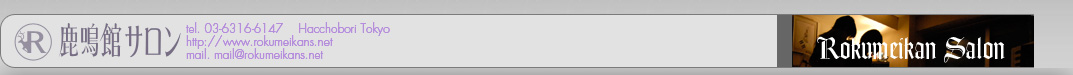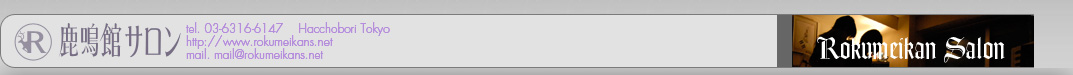・・・・・・・・ 序 文 ・・・・・・・・
いい本には二つの種類があると筆者は考えている。ひとつは読み終わったら、その本のことを誰かに語りたくなる本。もうひとつは、読んだことをそっと自分の内に仕舞っておきたくなる本。
語りたくなる本のことは鹿鳴館サロンの「読書感想会」というイベントで皆と語り合えばいい。
ゆえに、鹿鳴館プレゼント文庫は、もうひとつの、読んだことを他人にはそっと、そしてたいせつに隠しておきたくなるようなものを選ぶことにしている。
さて、その条件をクリアして、偶然、鹿鳴館プレゼント文庫を手にした人の数も多くなってきた。ここでは、どんなものがプレゼントされたのか、また、それをプレゼントとしてセレクトした理由は何だったのか。そうしたことを書き記していこうかと思う。
 |
 |
・・・・ 序 文 その2 ・・・・
いきなり横道にそれる。それもまた鹿鳴館サロンらしいのかもしれない。本当なら、ここから本の紹介に入らなければならないし、おそらく、読む人もそれを予想していたはずなのだ。 しかし、その前にどうしても、もうひとつ書いておく必要があった。
本の紹介をすると、すぐに推薦図書というのがイメージされる。著者はたしかに凄い人物である。凄いので、著者の考えや著者の好み、昨日の夜に何を食べたのかとか、好きな色とか、好きな作家とか、今日のニュースの感想について皆が興味があるに決まっている。それほど著者は凄い人物なのだ。
どれぐらい凄いかというと、著者の書いたものが三千年後に発見されたら、そのときには、世界的に評価されるに違いないほど凄い人物なのだ。
何しろ、千年後に発見されたって、たいていの文章はたいへんな価値を持つのだから、三千年も経過していたら、そりゃ凄い価値になるに違いない。
ところが、たいていの人は三千年zを待ってくれない。天の時間ならささいなものなのだが、ここでは待てないらしいので、今のこの時点という意味でいうなら、残念ながら、まだ、著者は評価されるに値しない。
著者の好みとか、ニュースに対する意見とか、もっと言うなら、著者が今日、何を食べたか、何を読んだかなどには誰も興味がないに違いない。つくづく三千年後でないのが残念でならない。
そんな著者が他人の著作を推薦することなど当然できようはずがないし、著者の好みを他人に明かす意味もない。
では、プレゼント文庫とは何なのか。これは、著者が他人に贈るならこんな本という話なのだ。他人に読んでもらいたい本ではない。他人に贈りたい本なのだ。その理由についてここで記すことは、それが鹿鳴館サロンとは何かということを記すことになるのだ。
それだけの理由なのだ。くれぐれも著者の推薦図書などという大それたものではないことをご理解願いたい。それを理解してもらえないと、なんだか著者がスター気取りしているようでいたたまれない。スター気取りは著者の容姿だけでたくさんなのだから。ただし、著者を見たことのある人は、著者の容姿について、その感想を述べてはいけない。著者がイケメンだと勘違いして女性がサロンに来てくれたら、それは幸いなのだから。
 |