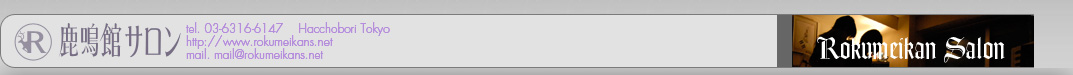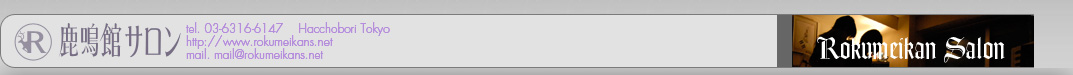・・・・・・・・ 序 文 ・・・・・・・・
男として生まれてきたからには一度は書評家というものになってみたいと思うものだ。もし、人生において一度も書評家というものになってみたいと思ったことがないなら、その人は男でないか、からっきしの臆病者か、あるいは小説の嫌いな人に違いない。
筆者も男と生まれ、子供の頃には森のケンカ屋と言われ、大人の頃には歩く三文図書館と言われ、さらに子供の頃には孤高の読書家とまで言われた男であるから、書評家にはなってみたかった。
書評家として、牛と闘い熊を倒し、エベレストを目指したかった。
しかし、すべては遅い。もう、書評家になるには体力がなさ過ぎるのだ。スピードがない。腕力がない。身体が硬い。
そこで、せめて、書評家の真似事をして諦めようかと思う。
 |
 |
・・・・ 序 文 その2 ・・・・
書評とは何だろうか。グルメレポートとか旅行ガイドとか商品カタログとかのようなもので、その対象が書籍だから書評なのだろうか。そうだとすれば書評という文学はずいぶんと悲しい文学ではないか。書評というものが書籍のただの紹介なのだとすれば、それは悲し過ぎる。書評とはそんなものでいいのだろうか。しかし、書評が、作者に対する挑戦状になっていたのでは、これはあまりに大仰である。そんなたいそうなものでも書評はないだろう。
では、書評とは何なのだろうか。
他人の身体を借りて生きる寄生虫なのだろうか。本当にそんなものなのだろうか。確かに、書評というものは他人の書籍なしには成り立たないものなのかもしれない。それはそうだ。そして、そうしたものは文学とは言えないし芸術でもない。しかし、それでは書評は悲し過ぎる。あまりに悲しいので、書評だけで、しっかりとした文学になるようなものを作ってみたいと思った。
と、そんな嘘を書いておこうかと思う。
本当は違う。鹿鳴館が電子書籍を出版しようとしたときに、そのラインナップがあまりにも寂しいことになりそうなので、見せかけの商品を並べておいたらいいだろうとはじめたのだ。見せかけの商品を並べて売り切れにしておけばいいだろうと思ったのだ。電子書籍で売り切れというのも不思議だが、そこも面白いと考えたのだ。そんなくだらないことを考えるような輩なものだから、やりはじめたら面白くなってしまって、本末転倒して、ちゃんとした商品のないまま、書評そのものが作品化されてしまったのだ。
そして、この冒頭が書かれたのである。ここまできたらいっそ空想図書館まで頑張りたい。
|